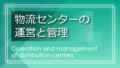物流センターでの「ピッキング」は、出荷指示に基づき、保管場所から指定された商品を集める業務です。一見単純な作業に見えますが、そのスピードと正確性は、物流コストや顧客満足度に直結します。
「倉庫内の移動時間が長すぎる…」
「なぜかミスが増えてきた…」
もし、このようなお悩みをお持ちなら、現在のピッキング方式が現場の状況に合っていないのかもしれません。
ピッキングには、代表的な方式として「シングルピッキング」と「トータルピッキング」の2種類が存在します。本記事では、この2つの方式の違いと、それぞれのメリット・デメリットを解説するとともに、現場ですぐに試せる効率化のヒントまで踏み込んでご紹介します。
シングルピッキング(摘み取り方式)の特徴
シングルピッキングは、1つの注文ごとに必要な商品をすべて集める、最も基本的な方法です。作業者はピッキングリストを手に、リンゴ狩りのように必要な商品だけを摘み取っていきます。
作業フローは「ピッキング→検品→梱包」と非常にシンプルで、ピッキングと仕分けが同時に完了するのが特徴です。
メリット
● 作業が単純で習得が容易: 1つの注文を完了させるという単純な作業のため、経験の浅い作業員でもすぐに業務に慣れることができます。
● 出荷までの時間が短い: ピッキング後に仕分け作業が不要なため、急な注文や個別の注文にも迅速に対応できます。
● ミスが起きにくい: 注文ごとに作業が完結するため、他の注文の商品と混ざってしまうといった間違いが起こりにくいのが特長です。
デメリット
● 移動距離が長くなる: 注文の数だけ倉庫内を往復する必要があるため、注文件数が増えるほど作業者の移動距離が長くなり、非効率になる可能性があります。
● 作業の重複が発生しやすい: 複数の注文に同じ商品が含まれている場合、その都度同じ場所へ商品を取りに行くという無駄な動きが発生します。
● 作業効率が熟練度に依存しやすい: 作業は単純ですが、裏を返せば個人の経験値に頼る部分が大きくなります。そのため、倉庫内を熟知したベテランと新人では作業スピードに大きな差が生まれやすいという側面も持っています。
最適なケース
通信販売の物流センターように、取り扱う商品の種類が多く、1注文あたりの商品数が少ない多品種少量の出荷に最適です。
《改善のヒント》 シングルピッキングの移動距離を短縮するには?
● ロケーション管理の最適化(ABC分析): Aランク品を作業者の動線に近い場所に配置することで移動距離を大幅に短縮できます。また、取り出しやすい腰の高さの棚に置くことで、作業効率や生産性の向上にもつながります。
● 動線の固定化: 倉庫内に一方通行のルールを設けるなど、作業者の動線を固定化することで、無駄な動きや作業者同士の衝突を防ぎ、スムーズな移動を促します。
トータルピッキング(種まき方式)の特徴
トータルピッキングは「種まき方式」や「バッチピッキング」とも呼ばれ、複数の注文を1つのグループ (作業をしやすくするための「ひとまとまり」)にまとめ、そのグループ内で必要な商品の総量を一度にピッキングする方法です。まず商品ごとの総量をまとめて集め、その後、専用のスペースで各注文へと商品を振り分け(仕分け)ます。畑に種をまくように商品を各注文の箱に振り分けていく様子から、種まき方式と呼ばれています。
作業フローは「総量ピッキング→検品→仕分け→検品→梱包」となり、「仕分け」の工程が追加されます。
メリット
● 移動距離を大幅に短縮: 複数の注文の商品をまとめて取りに行くため、倉庫内の移動距離と時間を最小限に抑え、作業効率を格段に向上させることができます。
● 大量の注文を効率的に処理: 一度に多くの注文を処理できるため、出荷件数が多い場合に非常に効率的です。
● 精度の向上と検品作業の簡略化: 仕分け完了時に商品が余らなければ、ピッキングした総数が正しいことの確認にもなるため、数量間違いの防止につながります。これにより、別途行う数量チェック(検数)の作業を簡略化できます。
デメリット
● 仕分け工程と専用スペースが必要: ピッキング後に商品を注文ごとに仕分ける工程が必須となり、そのための作業スペースを確保する必要があります。
● 作業工程の複雑化とミスのリスク: 工程が増える分、作業が複雑になり、特に仕分け段階で商品を入れ間違えるといったミスが発生するリスクが生まれます。
● リードタイムの長期化: 効率を上げるには、ある程度の注文数が溜まるまで作業を開始できないため、注文が少ない状況では、その効果を最大限に発揮できません。また、すべての仕分けが終わるまで次の工程に進めないため、出荷が遅れる一因となります。
最適なケース
コンビニエンスストアやスーパーマーケットの店舗配送のように、出荷先が比較的少なく、特定の商品を大量に出荷する場合に有利です。少品種大量のケースで効果を発揮します。
《改善のヒント》 トータルピッキングの仕分けミスを防ぐには?
● デジタルアソートシステムの導入: 仕分け棚の間口に設置されたランプとデジタル表示器が、次に商品を投入すべき場所と数量を指示してくれます。作業者は光った場所に入れるだけなので、直感的な作業が可能になり、ヒューマンエラーを大幅に削減できます。
● ハンディターミナルの活用: 商品バーコードと仕分け先のバーコードをハンディターミナルでスキャンすることで、システムが正誤を判断します。これにより、アナログなチェック作業をなくし、精度とスピードを両立させることができます。
【比較表】自社に最適な方式は?
ここまで解説した2つの方式の違いを、以下の表にまとめました。
| 項目 | シングルピッキング | トータルピッキング |
| 別名 | 摘み取り方式 | 種まき方式、バッチピッキング |
| 作業の流れ | 注文ごとに商品を集める | 全注文の商品をまとめて集め、後で仕分ける |
| メリット | ・作業が単純 ・出荷までの時間が短い ・ミスが起きにくい | ・作業者の移動距離が短い ・大量の注文を効率的に処理 ・精度の向上と検品作業の簡略化 |
| デメリット | ・注文が多いと移動距離が長くなる ・作業の重複が発生しやすい ・作業効率が熟練度に依存しやすい | ・仕分け工程とスペースが必要 ・作業工程の複雑化とミスのリスク ・リードタイムの長期化 |
| 最適なケース | 多品種少量(EC通販など) | 少品種大量(店舗配送など) |
実際の現場では「完全にどちらか一方」を選ぶ必要はありません。
例えば、出荷量の多い特定の商品だけトータルピッキングで処理し、残りの多品種な商品をシングルピッキングで対応するといった「ハイブリッド運用」も非常に有効です。
さらに、担当エリアを決めてリレー形式でピッキングを行う「ゾーンピッキング」など、他の方式と組み合わせることで、より自社の状況にフィットした最適な運用を構築することが可能です。
まとめ:正しい方式の選択と「改善の継続」が鍵
本記事では、シングルピッキングとトータルピッキングの違いと、それぞれの改善のヒントについて解説しました。自社の状況を正しく把握し、適切なピッキング方式を選択することが、業務効率化の第一歩です。
今回ご紹介した「ロケーション管理の見直し」や「デジタル機器の活用」といった施策を組み合わせることで、ピッキングの生産性はさらに向上するでしょう。
まずは自社のピッキング作業を、改めて見つめ直してみてはいかがでしょうか。
(文責:高山 健)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★掲載された記事の内容を許可なく転載することはご遠慮ください。
ロジ・ソリューションでは、物流に関するさまざまな支援させていただいております。
何かお困りのことがありましたらぜひお声掛けください。(お問い合わせはこちら)
(ロジ・ソリューション(株) メールマガジン/ばんばん通信第583号 2025年10月8日)